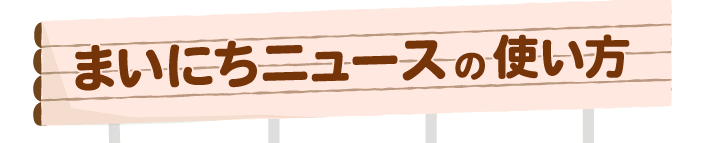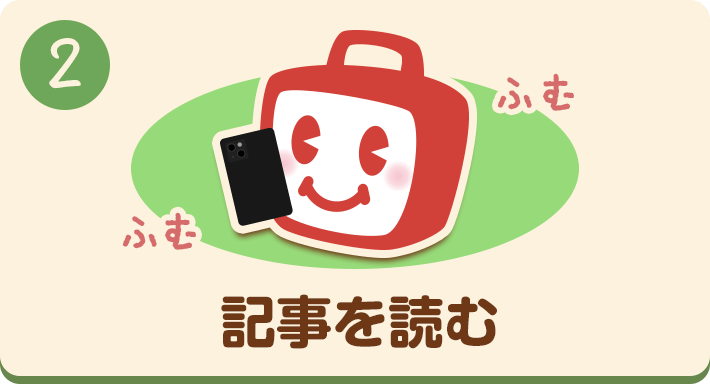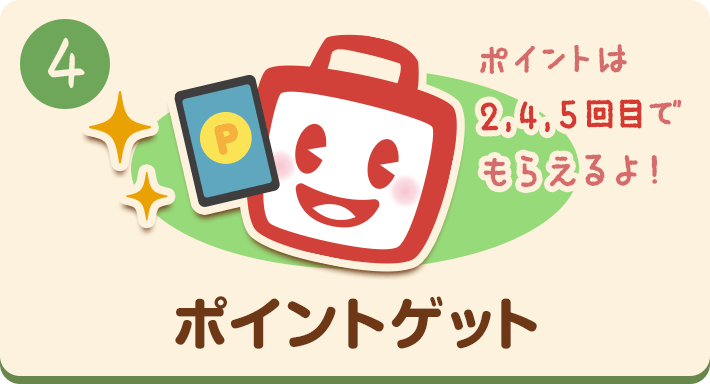人類の歴史は、先人たちのひらめきや発明によって新たな扉を開いてきたといえるかもしれません。それは軍事の分野も同様で、様々な新兵器の登場が戦争の様相を一変させてきましたが、「新兵器」になれなかった「珍兵器」も存在しました。
高所から機銃掃射を可能にするには
理想を形にしてみたら、実用性が皆無になり結局使いものにならなかった、ということは、古今東西枚挙にいとまがありません。第2次世界大戦中にイギリスで開発された「プレイング・マンティス」なる機関銃搭載の豆戦車も、その点では決して引けを取らない車両といえるでしょう。
 イギリスのボービントン戦車博物館に展示されている「プレイング・マンティス」の試作2号車。アームは寝た状態(柘植優介撮影)。
イギリスのボービントン戦車博物館に展示されている「プレイング・マンティス」の試作2号車。アームは寝た状態(柘植優介撮影)。
古代の戦いより、矢を射るにしても銃を撃つにしても、敵を見下ろす場所から放つ方が有利であり、なおかつ高い位置からなら障害物で遮られることもありません。さらに見晴らしもきくため、目標の動きも把握しやすくなります。
これと同じ考え方で、装甲車が搭載する機関銃を極力高い位置に持って行き、見下ろす形で撃つことができれば戦場では有利になると、第2次世界大戦前のイギリスで考えた人がいました。その名はアーネスト・ジェームズ・タップ。彼は商用車の修理や改造を請け負う自動車技師で、自身の理想の「機関銃戦車」を作って、イギリス陸軍に売り込もうと考えました。
彼は、まず1937(昭和12)年に先行して特許を取得し、次いで第2次世界大戦が勃発した後の1943(昭和18)年から本格的に開発をスタートします。
タップは手始めに、自分の構想が問題ないか確認するための実証用車体を作ります。そのため最初の試作車は、小さな装軌(いわゆるキャタピラー)式車体に上下動する箱型アームを取り付けただけのものでした。
この試作1号車で動作を確認したのち、タップは改めて試作2号車の開発にとりかかります。今度は当時、イギリス陸軍が運用していた装軌式汎用装甲車である「ユニバーサル・キャリア」を流用しました。
車酔いのひどい戦車が誕生
「ユニバーサル・キャリア」は、全長3.6m、全幅2.1m、重量3.8tというオープントップ構造の装甲車で、操縦手以外に5人から6人が搭乗できます。兵士ではなく物資や弾薬などを積むこともできるほか、対戦車砲や迫撃砲を積んで自走砲として用いることも可能でした。
 「プレイング・マンティス」がアームを上げた状態。最上部の銃塔は7.7mm機関銃を連装で装備する(画像:帝国戦争博物館/IWM)。
「プレイング・マンティス」がアームを上げた状態。最上部の銃塔は7.7mm機関銃を連装で装備する(画像:帝国戦争博物館/IWM)。
試作2号車は、この車体の中央に上下動する箱型の大型アームを装備し、そのアームの先端に乗員室が取り付けられていました。大型アームは車体後部に支点となる軸(ピボット)があり、ヘビが鎌首を持ち上げるかのように乗員室がせり上がります。
その乗員室には操縦手と銃手の2名が腹這いで乗り込み、その上部には銃手が操作する銃塔が搭載されていました。
箱型アームは、射撃する際は最大55度の角度まで持ち上がり、最高で3.48mの高さから機関銃を撃つことができ、このアームを上げた状態で走ることも可能でした。
なお、その銃塔付きアームを上げた外観が、昆虫のカマキリに似ているということで、英語で「祈るカマキリ」を意味する「プレイング・マンティス」という愛称が付けられました。
完成した試作2号車はイギリス陸軍に引き渡され、運用試験が開始されます。すると、さまざまな問題点が露呈しました。なかでも問題視されたのは、操縦手がコントロールしにくい点と、乗り心地が最悪だった点です。
操縦手が銃手とともに乗り込むのは箱型アームの先端です。アームが寝た状態のときはまだよいものの、アームを上げた状態だと足元が見えないまま前後左右に車体を動かすのは非常に難しいものでした。乗り心地も、不整地を走るとアームが上がった状態では揺れが増幅し、乗員が乗り物酔いをするほどひどかったそうです。
こうして、イギリス陸軍は実用に堪えないと判断を下し、「プレイング・マンティス」は1944(昭和19)年に開発中止となりました。なお試作1号車は廃棄されましたが、試作2号車はイギリスのボービントン戦車博物館で保存展示されています。