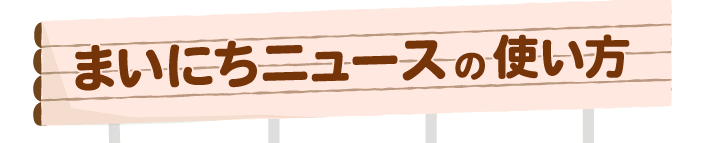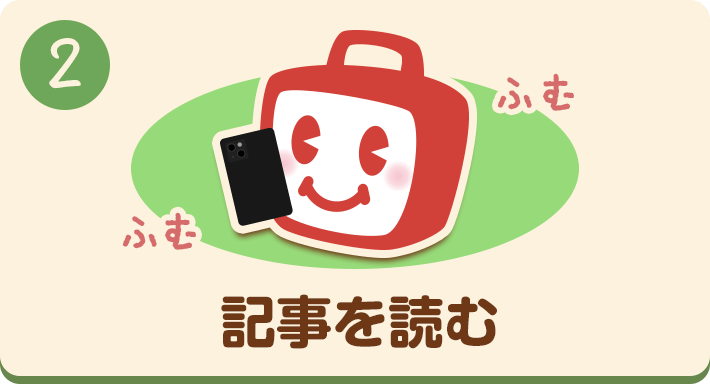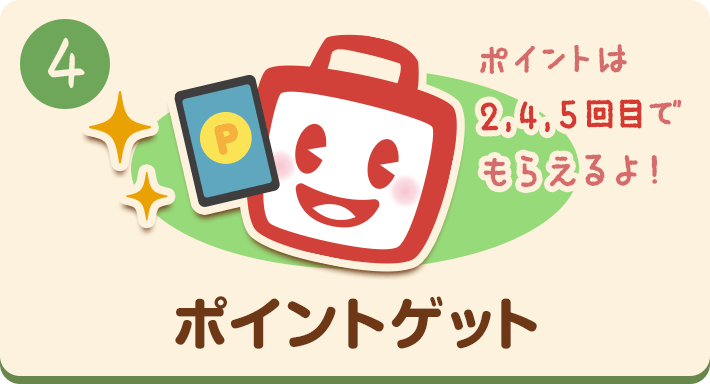約20年間、京王電鉄で運行されてきた「準特急」。急行の格上、特急の格下という位置づけで、平成以降は京王唯一の種別でした。なぜ「快速急行」ではないのか――「特急」にこだわる「京王らしさ」が見えてきます。
現在は京王電鉄のみの「準特急」
京王電鉄は2022年春のダイヤ改正で「準特急」の種別を廃止します。正確にいうと「準特急」を「特急」とし、現在の特急はなくなります。ややこしいですが、特急の停車駅を増やして準特急と同じにするので、もう全部「特急」にしますよ、というわけです。いずれにしても日本で唯一、令和の時代まで京王電鉄が使ってきた「準特急」の種別は消滅します。
 京王線の種別「準特急」(画像:写真AC)。
京王線の種別「準特急」(画像:写真AC)。
思い返せば、2001(平成13)年のダイヤ改正で「準特急」が新設されたときは戸惑いました。準を冠する列車種別といえば当時も、「準急行」略して「準急」が広く使われていました。急行に準ずる列車ですから、同じ路線でも急行より停車駅が多い種別です。
「準特急」の「準」の字は「準急」の印象が強く、サービス面で格下という印象です。2001年の違和感はそこでした。わざわざ特急の格下の列車種別を作るなら、急行の格上の「快速急行」でも良かったはず。「快速な急行」の方が良い印象で、スピード感もあります。近隣の西武鉄道、東武鉄道、小田急電鉄は「快速急行」を採用しています。
ちなみに「準特急」は過去にも小田急電鉄や近鉄で採用されていました。どちらも特急料金が必要な「特急」を運行していましたが、準特急は「特急の速度だけど特急レベルの車両を使わない」位置づけでした。国鉄の急行と準急の関係に似ています。
当初は違和感もあった京王の「準特急」も、さすがに20年経ったいまは慣れてきました。それだけに、こんどは消えてしまうことが寂しくもあります。
「快速急行」じゃダメ…?
なぜ京王電鉄は「快速急行」ではなく「準特急」としたのかを考察してみました。理由として「新宿発」「わかりやすさ」「スピード感」があるようです。
「準特急」が登場する2001年ダイヤ改正の直前、京王線・相模原線の列車種別は「各停」「通勤快速」「快速」「急行」「特急」でした。
京王線は都営新宿線と直通運転しますが、上記の種別のうち「特急」だけが新宿発着でした。そのような中、「準特急」も新宿発着で設定されました。つまり「特急」と「準特急」は「新宿発着で乗り入れなし」と認識できました。
「わかりやすさ」については、「“快速”が増えすぎる問題」の回避でしょう。すでに「通勤快速」「快速」がある状態で「快速急行」があると紛らわしいと思われます。
「スピード感」は通過駅数の比較から推察されます。じつは京王線新宿発着の「急行」はかなり俊足です。京王新線を除く京王線全32駅のうち半数以上の18駅を通過します。準特急が設定された2001(平成13)年当時、特急はさらに7駅を通過し、さらなるスピードアップを図っていました。準特急は特急停車駅に分倍河原、北野を追加しただけ。京王線に限れば急行の仲間というより、特急の仲間と考えられます。
急行の停車駅を減らした「快速急行」ではなく、特急の停車駅を増やした「準特急」しとた理由は、ライバル意識にもありそうです。「京王多摩センター」駅と「小田急多摩センター」駅は、どちらからでも新宿へ行けます。ただし小田急は「快速急行」、京王は「準特急」です。準特急の方が“速そう”ですね。2022年春のダイヤ改正からは、「快速急行」対「特急」となります。名前が変わっただけですが、さらにイメージアップします。
有料ライナーの下位に2種類の特急は不要?
「準特急」が消滅する理由は、前出のとおり特急の停車駅を増やすためです。一般に速達列車は「停車駅を減らせば早く着く」「停車駅を増やせば利用客を増やせる」という、相反する要素があります。「特急の停車駅を増やす」という判断には、リモートワークや時差出勤、外出自粛の高まりによって、全体的な乗客数が減っているという背景があります。特急の停車駅を増やして「お客様が乗りやすく」というわけです。
 特急の上位種別として「京王ライナー」「Mt.TAKAO号」が登場。5000系電車(右)が使われる(2021年10月、大藤碩哉撮影)。
特急の上位種別として「京王ライナー」「Mt.TAKAO号」が登場。5000系電車(右)が使われる(2021年10月、大藤碩哉撮影)。
そこで特急の停車駅を増やす検討をしたら、準特急と一緒になってしまった――では特急を廃止して準特急を残すかといえば、そうはいきません。「準特急」は「特急」あっての「準」ですから、最上位種別に「準」がついてはおかしいですね。その結果、「準特急は特急になった」というわけです。
準特急の登場時と現在の違いとして「京王ライナー」「Mt.TAKAO号」の存在も見過ごせません。京王ライナーは2018年に誕生した有料座席指定列車です。当時、新宿~府中間は全通過。2022年春からは明大前~府中間、または明大前~京王永山間をノンストップで走ります。「Mt.TAKAO号」も2018年に登場した臨時列車でしたが、2022年春からは土休日の通年運行となります。こちらも明大前~府中間はノンストップとなる予定です。
特急の上位に新たな速達列車が登場したわけです。そうなると、下位の特急列車は2種類も必要なし。むしろ停車駅を増やしてそろえて集客しようという判断もあったことでしょう。準特急の利用者が多いから、準特急の方に統合したわけです。つまり、2001年に「準特急」として設定した列車は正しい判断でした。
今後、京王電鉄で準特急は復活するでしょうか。他社からは誕生するでしょうか。そのとき、準特急はどんな使命を持って走り始めるでしょうか。その時になったら、この記事を思い出すと懐かしく、楽しいかもしれません。