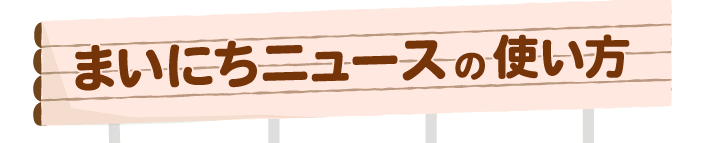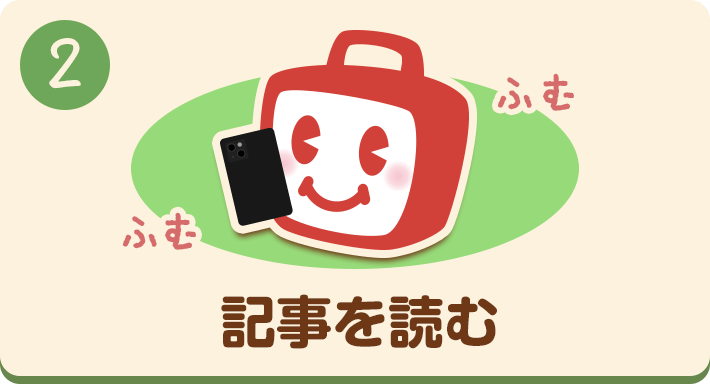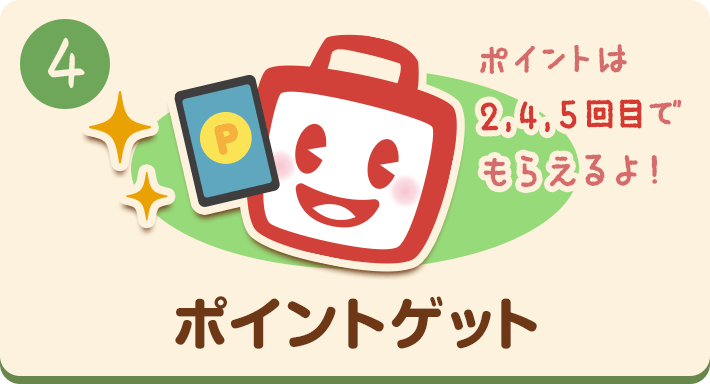日本では男女が結婚する際に、男性または女性の姓(名字)に統一する「夫婦同姓」が、法律で義務付けられています。結婚に伴い名字を変える場合は、免許証や銀行口座などの名義変更の手続きを行わなければならず、大きな負担となります。そのため、夫婦が望む場合は、結婚後も結婚前の名字を自由に名乗れる「選択的夫婦別姓制度(選択的夫婦別氏制度)」の導入を求める声が高まっています。
ところで、結婚の際に妻の名字に変更した経験がある、評論家の真鍋厚さんによると、夫婦同姓の制度が導入されたのは明治時代だといいます。今回は、真鍋さんが、妻の名字に変更した体験を踏まえながら、夫婦同姓が導入された経緯について、さまざまな資料を基に解説します。
1898年の民法公布で夫婦同姓の仕組みが確立
経団連が1月17日、政府に選択的夫婦別姓制度の導入を求めたことが話題となっています。「結婚後に夫婦が同じ姓を名乗ることを義務付ける日本の制度が企業活動を阻害している」などと、企業活動の面から問題提起した形ですが、SNSでは一定の支持が集まりました。
選択的夫婦別姓制度は、これまで最高裁で繰り返し否定されています。自民党の保守派が夫婦同姓にこだわっているなどといわれており、結婚すれば男女のうち、いずれかの名字を名乗るルールは変わりませんでした。
確かに夫婦別姓にすると「家族の絆が壊れる」「家族を解体する」と不安を表明する人々は一定数います。内閣府の調査でも、夫婦・親子の名字・姓が違うことについて、「家族の一体感・絆には影響がないと思う」と答えた人が61.6%と過半数を占める一方で、「家族の一体感・絆が弱まると思う」と答えた人が37.8%と、およそ4割に上ることが分かっています(※1)。
しかし、婚姻制度の歴史を振り返ると、意外な姿が見えてきます。なんと当初は「夫婦別姓」が原則だったのです。もっとも、古い仕組みが伝統だと考えた場合、夫婦別姓こそが本来の日本の伝統となるのです。この時点でいわゆる伝統重視の「解体論者」の前提は崩壊してしまいます。以下、その理由を簡単に説明します。
日本法制史学者の熊谷開作氏は、明治維新以前の江戸時代について、「多くの庶民は、農村でも都市でも『氏』とは無縁であった」と述べています。つまり、そもそも名字などなかったのです。そして、「明治初年から民法の実施が近づいてきた同二十年代の後半まで、妻は婚姻の後も生家の氏を称するものとされてきた」と解説しています(「日本の近代化と『家』制度」、法律文化社)。
「生家の氏」とは、生まれた家の名字のことです。例えば、どこかの家に嫁いでも、佐藤家に生まれたら佐藤のまま、山田家に生まれたら山田のままだったのです。重要なのは、その人が「どこの家」の出身なのかが分かることだったからです。熊谷は、「『夫ノ家ノ氏』の観念は、日本では、それほど古いものではなかった」としています(前掲書)。
また、儒教の影響を指摘する識者もいます。中国哲学者の加地伸行氏は、「中国・韓国(朝鮮)、そして明治三十一年以前の日本―これらの国々では、結婚後も妻は生家の姓を名乗っていた。その根本理由は、儒教における『同姓不婚』の原則によるものである」と主張しています(『儒教とは何か 増補版』、中公新書)。これは同族間の結婚を避ける目的があったからです。
1898年(明治31年)に民法(旧法)が公布され、現在のような夫婦同姓の仕組みが確立されました。歴史的に見ると、夫婦別姓という儒教文化圏の慣習を廃止して、夫婦同姓というキリスト教文化圏のファミリーネームを新たに採用したといえます。
民法学者の中川善之助氏は、「婚姻をしても、夫婦夫々の氏に変動は起こらないというのが、キリスト教国を除く世界諸民族の慣習法であった」と述べています(※2)。
恐らく、不平等条約の撤廃などで近代的な法制度の整備を急いでいたことが背景にあったのでしょう。けれども、戦後の民法改正でも婚姻制度における夫婦同姓は引き継がれました。
今の世界の状況を見ると、日本だけが夫婦同姓を強制している特殊な状態になっています(※3)。2010年に法務省が行った調査によると、アメリカやイギリス、ドイツなどは夫婦別姓が選べるほか、韓国や中国、フランスなどは原則夫婦別姓でした。
女性の95%が結婚で名字を変更
今回の経団連の要望は、パスポートの氏名とビジネスネームが一致しないことで、海外出張先のホテルで宿泊を断られるなど、具体的なビジネスの場面で障害があることを訴えたものですが、これは以前から名字を変えた側の名義変更の負担として指摘されていました。
先述の内閣府の調査では、52.1%の人が、夫婦同姓について「何らかの不便・不利益があると思う」と答え、その8割以上が「名義変更の負担があるなど、日常生活上の不便・不利益がある」と答えています。
実態として、結婚して名字を変える人は女性が圧倒的に多く、内閣府によると、全体の約95%を占めるということです。
ちなみに筆者は、結婚して名字を変えた5%の男性のうちの一人です。名字の変更後に起こった出来事は、大半の女性にのしかかる負担を考える上で貴重な経験でした。まず、両親から「婿養子になるのか」「なぜこちらが名字を変えるのか」と言われたことが印象に残っています。
最終的に両親は妻の名字に変更することを受け入れてくれましたが、家族内または家族同士のトラブルに発展するケースも少なくないと聞きます。どちらかの家族が名字を変えることに反対して、それが結婚の障壁になったり、男女の仲に亀裂が入ったりするのです。当然、仕事に支障を来すため、双方が「変えたくない」と主張し、平行線をたどる場合もあります。
筆者の場合は、免許証や通帳、社会保険など、諸々の手続きが思いのほか手間がかかったほか、職場で旧姓を「通称」として使用することを選んだこともあり、いろいろと面倒な確認作業が生じました。もしこの名義変更に伴う社会的なコストを計算すれば、心理的なストレスも含めて相当なものになるのではないでしょうか。
仮に現在提案されている選択的夫婦別姓制度が実現すれば、行政の窓口など公的な手続きをはじめとする膨大なコストの削減となり、個々の負担も驚くほど解消されると思います。改正点としては、夫婦同姓と夫婦別姓のいずれかを選べるようにするだけです。これまで通り同姓が良い人はそれを選び、別姓が良い人はそれを選ぶだけです。
それでもまだ不安な人たちは存在することでしょう。「夫婦別姓の人ばかりが増え、家族や夫婦の形がおかしくなるのではないか」と考える人たちです。これにはまったく根拠がありません。先述のように明治以前は、庶民に名字はなく、明治になってもしばらくは夫婦別姓だったのですから。
さらに言えば、制度の改正で夫婦別姓が急増するとも思えません。女性の場合、夫の名字に変えることで結婚を実感する人も多いからです。夫婦別姓が可能になった場合にそれを選ぶかどうかを聞いた民間の調査があります。特に女性の夫婦同姓に対する憧れが強いという結果が出ており、夫婦別姓を選ぶと回答したのは男女とも2割程度でした(※4)。
古くから続いてきた制度のひずみを修正したり、変更したりする際、まるでその制度によって特定の価値観が支えられてきたような誤解がよく起こります。文化や慣習は非常に強固なものなので、通常、オプションが1つ増えた程度では容易に変わりません。なぜ不安を口にする人がいるのでしょうか。
それは「これが当たり前で普通のこと」というように、自分を正当な場所に位置付けることで得られる安心感が失われつつある時代だからです。けれども、私たちにとって、これは自由に自分を定義できるという利点と表裏一体のものです。そのような社会変化の必然をしっかりと見据えた上で、誰かを批判したくなる誘惑と向き合う必要があるようです。
【参考文献】
(※1)「家族の法制に関する世論調査(令和3年度)」(内閣府)
(※2)「法学セミナー」152号/「民法改正二十年(回想録捨遺集)」(日本評論社)
(※3)「参議院議員糸数慶子君提出選択的夫婦別姓に関する質問に対する答弁書」
(※4)「20代~30代独身男女、『夫婦別姓』賛成5割、実際に『別姓にしたい』は2割~女性の5人に1人は夫婦同姓に憧れないと回答~」(QOM総研)
評論家、著述家 真鍋厚