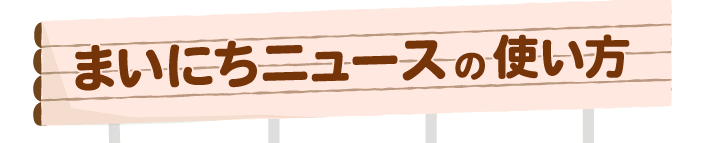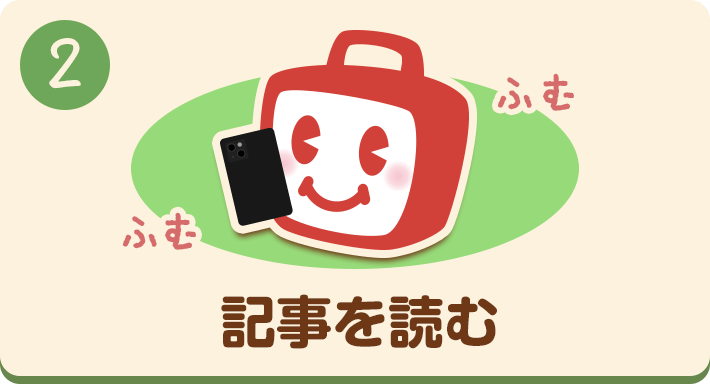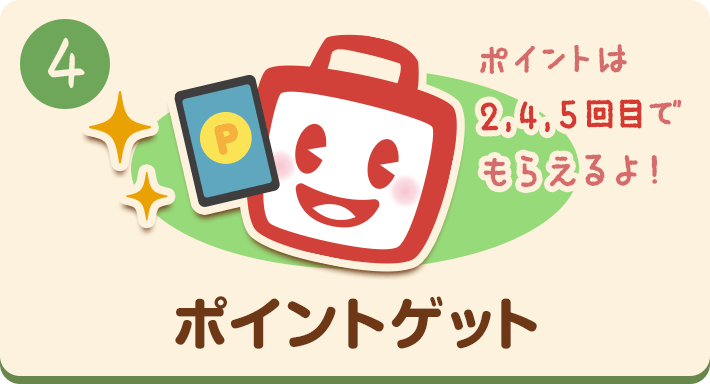空中停止できる飛行機は、ごく一部を除くとほぼ見られません。しかし第2次世界大戦でドイツが使用したFi156は、抜群の安定性でそれに近いことを行っていました。またその性能を用いて、歴史に刻む作戦の成功にも貢献しました。
見た目「空中停止」を行うために必須の性能とは
固定翼機、いわゆる飛行機は、F-35B戦闘機のような垂直離着陸(VTOL)機などのごく一部を除くと、ヘリコプターのホバリングのように空中で停止することはできません。しかし、かつてドイツにはそれに近いことをできた飛行機がありました。第2次世界大戦中にドイツ空軍が用いたFi156「シュトルヒ」です。この機体はどのように「空中停止」できたのでしょう。
 第2次世界大戦中、フィンランドに駐留していたドイツ軍で用いられたFi156「シュトルヒ」(画像:フィンランド国防省)。
第2次世界大戦中、フィンランドに駐留していたドイツ軍で用いられたFi156「シュトルヒ」(画像:フィンランド国防省)。
そもそもFi156のいちばんの特徴は、抜群の短距離離着陸(STOL)性能で、離陸時の滑走距離は50m、着陸はその半分の20mで行えました。
なぜ、これほどの短い距離で離着陸ができるかというと、それはFi156の外観的特徴のひとつである、機体サイズに比して大きな主翼によるものでした。
一般的に、主翼は広いほうが大きな揚力を生み出します。揚力が大きければ大きいほど離陸しやすくなり、なおかつ飛行中の安定性も高まります。しかし、大きな主翼は速度を出す際には空気抵抗の元凶になり、スピードを追求するには不利です。Fi156は飛行安定性を重視しており、最大速度は175km/hにとどまりました。
速度を代償に獲得した飛行安定性は格段に優れており、飛行機としては極端に遅い50km/hという低速でも飛ぶことができました。この超低速飛行の時に、同程度の風速で向かい風が吹いていると速度は相殺されて10km/h以下になり、端から見ると、あたかも空中で停止しているようにしか見えません。
50km/hを秒速に直すと約13.9m/sです。気象庁によると、平均風速10m/s以上15m/s未満は「やや強い風」で、電線が揺れ始める、道路の吹流しの角度が水平になるレベルであり、この程度の風ならばそれほど稀ではありません。
このようにFi156は、高揚力性を有する優れた飛行安定性によって、風の向きによっては速度を相殺することで、事実上の「空中停止」ができたのです。
スピード激遅 それでも重宝された理由
Fi156が世に出る端緒になったのは、1935(昭和10)年にドイツ航空省が出した、空軍向けの新型連絡機の開発要求でした。
ドイツ航空省の要求は、飛行場が整備されていない前線で使用する軽量な偵察観測機で、優れた短距離離着陸性能と、全周にわたる良好な視界、そして操縦士(パイロット)以外に2名収容可能というものでした。
 Fi156「シュトルヒ」の機首部のアップ。操縦席のガラス部分が左右に大きく張り出しているのがわかる。これで良好な視界を確保していた(画像:フィンランド国防省)。
Fi156「シュトルヒ」の機首部のアップ。操縦席のガラス部分が左右に大きく張り出しているのがわかる。これで良好な視界を確保していた(画像:フィンランド国防省)。
各社はこの要求に応えられる試作機を開発しましたが、そのなかで最も優れていたのがフィーゼラー社の機体で、とくに短距離離着陸性能が優れていました。その結果、同社の機体が採用され、「Fi156」と命名されるとただちに量産が始まりました。
1937(昭和12)年にはドイツ空軍に配備され、前線部隊での運用が始まりました。具体的には、ドイツ陸軍の師団司令部に空軍のFi156が1機から2機ずつ出向する形で、これにより、陸軍は師団長や師団司令部レベルで空から偵察できるようになりました。また、それ以外にも数百kmの距離を短時間で行き来することが可能になったことで、命令書の迅速な送付や、高級幹部の前線と後方の速やかな往復ができるようになりました。
こうして、北は極寒のソ連内陸部やフィンランドから、南は北アフリカの砂漠地帯まで、様々な地でFi156は運用され、時には偵察や連絡飛行だけでなく、物資輸送や傷病兵の後送にも用いられました。
そのなかでFi156が、その飛行特性を最大限発揮した任務といえるのが、1943(昭和18)年9月12日に実施されたムッソリーニ救出作戦でしょう。
ヘリ代わりでFi156投入 ムッソリーニ救出作戦
第2次世界大戦中、イタリアの指導者であったベニト・ムッソリーニは、1943年7月24日にクーデターで失脚すると、8月末にイタリア半島中部のグラン・サッソ山中にあるホテルに幽閉されました。
 ムッソリーニ救出作戦でグラン・サッソの山の中腹に着陸したFi156「シュトルヒ」。この後、ムッソリーニを載せて飛び立った(画像:ドイツ公文書館)。
ムッソリーニ救出作戦でグラン・サッソの山の中腹に着陸したFi156「シュトルヒ」。この後、ムッソリーニを載せて飛び立った(画像:ドイツ公文書館)。
イタリアと同盟関係にあったドイツのヒトラーは、ムッソリーニが失脚した直後から保護を計画しており、ナチスの武装親衛隊を用いて彼を救出しようと動いていました。しかし、上述のホテルは山の中腹にあたる標高2000mの位置にあり、陸路で向かうにはふもとから伸びる一本道をひたすら上っていくしかなく、秘密裏に作戦を遂行するために空からの進入が計画されます。
そこで白羽の矢が立ったのがFi156でした。当初は世界初の量産ヘリコプターFa223が使用される予定でしたが、同機が壊れたために短距離で離着陸可能なFi156が急きょ代わりに投入され、山腹の狭い空き地に30m程度で着陸。復路はムッソリーニを載せ、重量オーバーながらもわずか75m弱の距離で離陸し、無傷での救出に成功しました。
なお、実はFi156は日本の空も飛んでいます。太平洋戦争開戦前の1940(昭和15)年、旧日本陸軍は、最前線で連絡や偵察、弾着観測、軽輸送など各種任務に用いるための多用途機を導入することを計画し、性能テストのために輸入していたFi156と国産の新造機を比較しました。
Fi156が性能的に優れていればライセンス生産する予定でしたが、国産の新造機が上回る性能を発揮したため、日の丸を付けたFi156はそれ以上増えることはありませんでした。一方、Fi156を上回る性能を出した国産機は、その後「三式指揮連絡機」として制式化されましたが、当初の任務では用いられずに、日本沿岸の対潜哨戒任務に用いられ、一部の機体は各種空母に載せられて船団護衛に従事しています。
ちなみに、Fi156には「シュトルヒ」という名称がつけられていますが、これはドイツ語で「コウノトリ」という意味です。