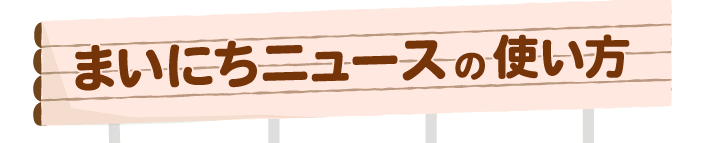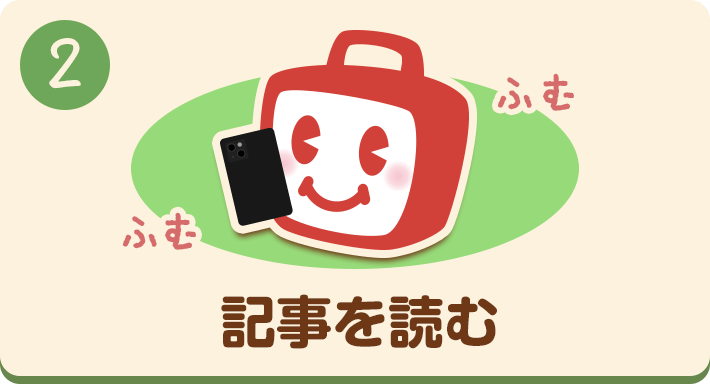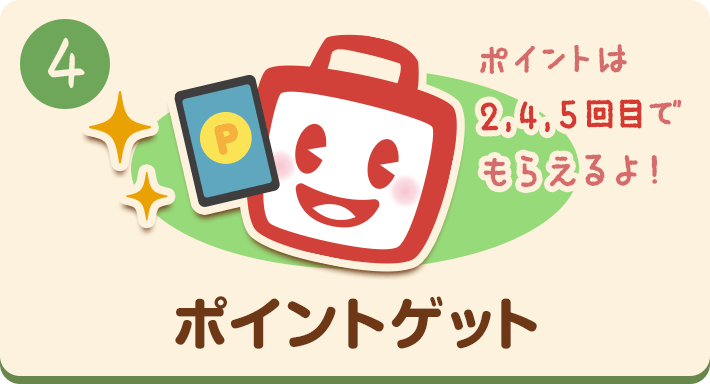春は人の動きがとても多い季節です。入社してくる人もいれば、会社を去る人もいます。このうち、退職でいなくなってしまった人が、残った有給休暇をすべて取得しながら、引き継ぎがいい加減だったり、自分が抱えていた問題を解決しないまま放置していたりして、本人がいなくなってから問題が噴出することが、残念ながらまれにあります。
まさに「立つ鳥跡を濁さず」ということわざとは正反対の状況ですが、「跡を濁されて」しまった場合、どのように対処すべきなのでしょうか。また、こういったことを未然に防ぐには、どのようにすればよいのでしょうか。
退職時の「引き継ぎ」期間設定には限界
まず、退職者が有休を取得するのは法的権利ですから、会社は拒否できません。できることとしては、会社側に認められた時季変更権を使って、「事業に支障があるから」と有休の日時を変更してもらうくらいです。しかしこれも突然の退職で、時季変更を行う余地がない場合はどうしようもありません。
また、十分な引き継ぎをできるようにと、就業規則に、例えば「退職の通知は退職日の2カ月前にすること」などと書いていても、民法では「従業員は、退職の2週間前までに通知すればよい」とされているため、法的拘束力はなく、「お願い」レベルの話になります。さらに、退職届の受理を拒否すると慰謝料を請求される可能性すらあります。
他にも、原則不可の有休買い取りの例外である「法定日数を上回る有休」や「退職時に残っている有休」を買い取ることと引き換えに、丁寧に引き継ぎをすることをお願いしたり、それもダメなら、引き継ぎのための休日出勤を命じたりするなどのアクロバティックな対応策もあるにはありますが、私はあまりお勧めしません。
そもそも「跡を濁す」去り方をするような人は(退職者と会社のどちらに非があるかは別として)、会社にネガティブな思いを抱いているわけでしょうから、法的にできるギリギリのところでなんとか時間を作ってもらったとて、問題が起こらないように引き継ぐかどうかなど分からないからです。
強制力でどうにかするのは愚策
そもそも、法律などの力による要請で物事を解決しようすること自体、退職者との関係性を悪くさせるのではと思います。何事もそうですが、人に強制力で何かをさせても、形だけは取り繕うかもしれませんが、心の入らない中途半端な行動では、あまり意味がありません。
それよりも、普通に退職者が自分から「きちんと引き継ぎをしなければ」と思うようになってもらうことが、本質的解決策ではないでしょうか。特に仕事の引き継ぎなどは、微妙なノウハウやコツ、人間関係の情報など、不文律的なところこそ重要なのですが、退職者の自発性がなければ、そういうことは引き継いではくれないでしょう。
【心構え1】退職決定後、冷たくするのは避ける
退職者が「飛ぶ鳥跡を濁さず」の気持ちになるには、何かネガティブな原因があって会社を辞めるのだとしても、会社に何らかの恩義を感じていなければならないでしょう。つまり、退職者がそういう恩義を感じるようなことを、会社側から実際にしてあげなくてはならないということです。
残念ながらよくあることですが、退職が決まったからといって急に冷遇したり、揚げ足を取るようなことをして懲戒にしたり報酬を下げたりしているようでは、恩義など感じるわけもなく、むしろ恨みが募るばかりです。そんなことをしていると、残る社員たちの側も「会社は人に冷たい」と思い、次の退職者への影響も大きいでしょう。
【心構え2】心の底からポジティブに送り出す
ですから、退職が決まっても、退職者への態度を変えないことです。むしろ、「これまで本当にありがとう」「残ってほしかったけれども、会社があなたの希望を満たせる場でなくて申し訳ない」という感謝やおわびの気持ちを持つべきです(たいていの退職は、会社にも何らかの非はあるでしょうから)。
退職者に言いたいこともあるかもしれませんが、120%ポジティブに送り出しましょう。また、去る人への批判なども言ってはいけません。フラットに退職理由を振り返ることは必要ですが、限られた責任者内でやればよいことです。
【心構え3】それでもダメなら「わが身の不徳」
そこまですれば、多くの人は「いろいろあったけれども、そう言えば少しは恩義もあったなあ。世界も狭いことだし、『飛ぶ鳥跡を濁さず』でちゃんと引き継ぎをしよう」と思ってくれるのではないでしょうか。
もし、そこまでしても難しければ、もう、残った人で後始末をするしかありません。その場合も、退職者を責めるより、わが身の不徳を振り返ることが、前向きな姿勢ではないかと思います。
「そういう常識のない人を採用してしまった」のか、「大切にしてもらったという恩義を感じないような対応をしていた」のか、いずれにせよ、それも根本的には会社の問題です。他責ではなく自責と捉えて、改善していくことで、「跡を濁される」ようなことは、徐々になくなっていくと思います。
人材研究所代表 曽和利光