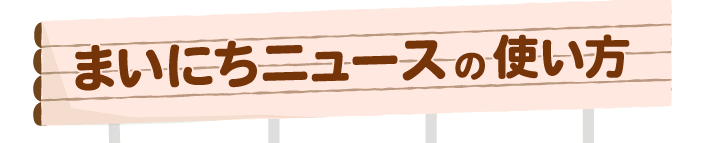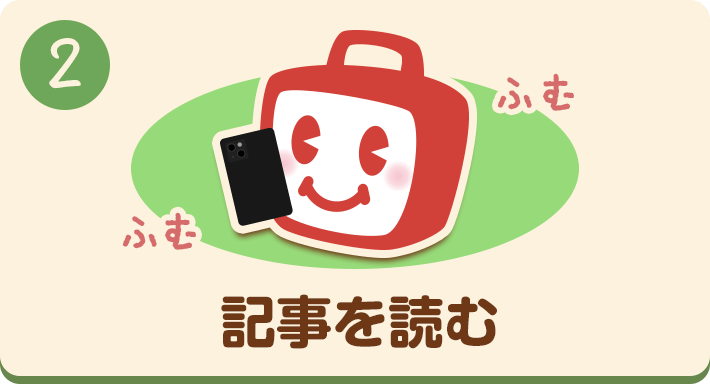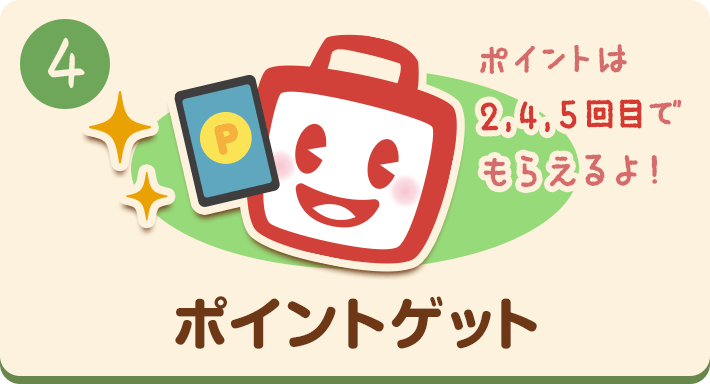島にはかつて住民がいた
太平洋戦争において、沖縄で激しい地上戦が行われたことは皆さんご存じだと思いますが、沖縄以外にも内地で激しい地上戦が行われた場所があります。それが東京都の小笠原村に属する硫黄島です。

ただし硫黄島には現在住民がいないことから、硫黄島の戦いも無人島のような場所で行われたと思っている人も多いかもしれません。
しかし今回紹介する石原俊『硫黄島』(中公新書)を読むと、戦場となった硫黄島にも人々の生活はあり、戦争に巻き込まれた住民がいたことがわかります。そして、彼らは戦後に故郷を失って「難民化」したのです。
硫黄島の戦いというと、クリント・イーストウッド監督で渡辺謙が主演した『硫黄島からの手紙』(2006年)を思い出す人も多いでしょう。
その『硫黄島からの手紙』には、短いながら渡辺謙が演じる栗林忠道(ただみち)中将が島を視察するなかで島民の家や子どもに目を留めるシーンがあります。そこで栗林は「島民は速やかに本土に戻すことにしましょう」と副官に言うのですが、ここからもわかるように硫黄島の戦い以前、そこには人々が暮らす社会がありました。
硫黄島に日本人の入植が始まったのは、1888(明治21)年からです。漁業や硫黄の採掘を目的に父島の船大工・田中栄治郎らが東京府に硫黄島の「拝借願」を提出し、開発が始まります。
当初はアホウドリの捕獲も行われましたが、すぐに個体数が減少し、また硫黄の採掘にも限界が見え始めたことから、産業の主力は農業へと移っていきます。硫黄島は温暖で、地熱もあり、また硝酸カリウム成分が豊富だったことから植物の生育が良好だったのです。
特異なプランテーション社会
1910(明治43)年にはサトウキビ栽培と製糖が開始され、1920年代後半以降は、コカやレモングラス、デリスなどの栽培も行われました。コカはコカインの原料であり、日本の製薬会社に買い取られ、そこでコカインに精製されインドなどの闇市場へと流れ、1940年代にはナチス・ドイツにも密輸されています。
硫黄島は特異なプランテーション社会でした。島民の多くは小作人であり、小作人は会社から指定された作物をつくる必要がありました。しかも、報酬は会社の指定店舗でしか使用できない金券で支給されており、生活必需品も拓殖会社が運営する商店から割高な価格で買うしかなかったと言います。
このような環境でしたが、食料事情は悪くなかったようです。硫黄島では野菜の自主栽培や家畜の飼育、漁業などによって自給自足が可能であり、「島では贅沢(ぜいたく)しましたよ」と回顧する元島民もいます。これについては、戦後の厳しい生活との対比で島での生活を「美化」している可能性もあると著者は指摘しています。
1941(昭和16)年に始まった太平洋戦争は、当初日本の優位に進みますが、次第に米軍が反攻に転じ、1944年7月にはサイパンを攻略します。日本本土はB29の航続距離圏内に入りますが、爆弾を搭載しての航続距離としてはギリギリであったため、1200m以上の滑走路がある硫黄島の存在がクローズアップされることになりました。

小笠原諸島の中心である父島は要塞(ようさい)化が進んでおり、また飛行場の滑走路の距離も短いことから、米軍は父島ではなく硫黄島を攻略することにしたのです。
硫黄島の守備を任せられた栗林中将は、今まで日本軍が行っていた水際迎撃作戦を捨て、硫黄島の天然の洞窟などを利用して壕(ごう)を整備し、ゲリラ戦を行う作戦を立てます。そのため、地下トンネルの整備が急ピッチで進められることになりました。
戦後「難民」状態となった島民
1944年6月に米軍空母による硫黄島への大規模な空襲が実施されると、栗林は民間人の引き揚げを決め、硫黄島の住民の多くが強制疎開の対象となります。ただし15歳から69歳の男性の多くは軍を手伝うこととなり、強制疎開のあとも160人が残留し、このうち103人が地上戦に動員されることとなりました。
このうち82人と、会社にだまされる形で島に残され、軍にその後徴用された11人の合わせて93人が亡くなっています。

1945年の2月から始まった硫黄島の戦いは激戦となりました。無謀な突撃を戒め、粘り強く戦うことを求めた栗林の作戦によって日本軍は予想以上の善戦をしたというのが一般的な評価でしょう。ただし、上陸直後から米軍は強力な妨害電波によって日本軍の通信を遮断し、それによって栗林の命令を無視して無謀な攻撃命令を出す将校も多かったようです。
生き残った兵士は硫黄島の壕のなかを「人間の耐久試験」だったと表現しており、悲惨な状況のなかで自決する者も相次ぎました。
終戦後の1946年1月、アメリカの決定によって小笠原群島、硫黄列島ですべての民間人の帰還・移住が禁止されます。父島においては、1876年(明治9)の日本併合以前から小笠原群島に居住していた先住民の子孫とその家族に限って居住が認められることとなりますが、硫黄島で居住を認められた者はいませんでした。
そして「無人島」となった硫黄島には、米空軍と沿岸警備隊の秘密補給基地が建設されていきます。1951年のサンフランシスコ平和条約でも小笠原群島や硫黄列島の施政権は返還されず、硫黄島民は事実上の「難民」状態となっていったのです。
故郷を失った島民の生活は困難を極め、著者は
「多くの日本国民(帝国時代の本土住民)には、敗戦直後の一時期を除けば、「戦前」よりも「戦後」が相対的に「豊かな」生活だったという自意識がある。(中略)これに対して、硫黄列島民の自己認識においては、「戦前」よりも「戦後」が苦難の経験として回想されがちだ」(158~159ページ)
と述べています。
「無人島」として固定化
1967(昭和42)年、小笠原群島と硫黄列島の施政権が日本に返還されます。
元硫黄島民の間でも帰還の期待が高まりますが、1970年に佐藤内閣が決定した小笠原諸島復興計画では「帰島および復興計画の対象は、当面父島および母島」と定められました。硫黄島に関しては、不発弾処理と火山活動の安全性の確認を理由に対象から外されてしまったのです。
その後も帰島へ向けた動きは進展せず、1984年には小笠原諸島振興審議会のもとに設けられた硫黄島問題小委員会が、火山活動が活発であること、コカが栽培禁止になっていること、漁業施設の建設が難しいことなどをあげ、硫黄島での定住は困難との結論を出しました。
この背景には、帰島に向けた環境整備のコストの問題とともに、「無人島」だった間に進行した硫黄島の軍事基地化があります。
硫黄島周辺では1970年代から自衛隊の対潜哨戒機(たいせんしょうかいき。敵潜水艦を捜索・探知・攻撃する軍用機)の訓練がしばしば行われるようになり、1981年には大村襄治(じょうじ)防衛庁長官が硫黄島を訪問し、基地の整備を進めると発言しました。そして、1984年には航空自衛隊の硫黄島基地隊が新設されています。
さらに1988年に騒音問題から厚木基地の艦載機の陸上離着陸訓練のうちの夜間離着陸訓練が暫定的に硫黄島に移されると、その後も硫黄島での訓練がつづくことになります。住民のいない硫黄島では騒音問題などに配慮する必要がなく、訓練を行う場所として好都合だったのです。
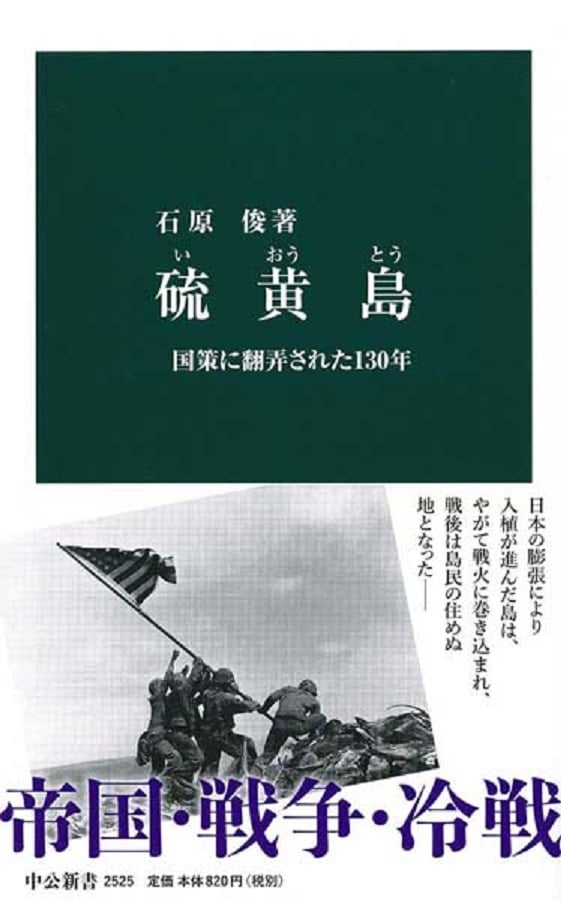
こうして、硫黄島は民間人が立ち入ることのできない島となりました。政府は旧島民に対して訪問事業を行っているものの、住民の帰還を前提とした施策は行っていません。硫黄島は「無人島」として固定化されつつあるのです。
本書では、硫黄島の歴史を島民へのインタビューなども交えながら丹念にたどっています。戦争が終わって四半世紀以上がたつわけですが、まだ「戦後」は終わったとは言えず、その終わっていない場所のひとつが硫黄島であることを教えてくれる本です。