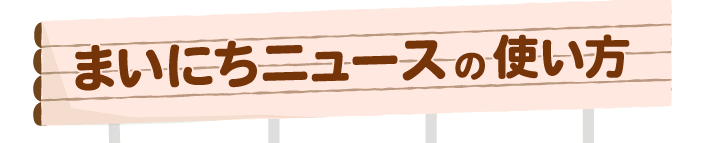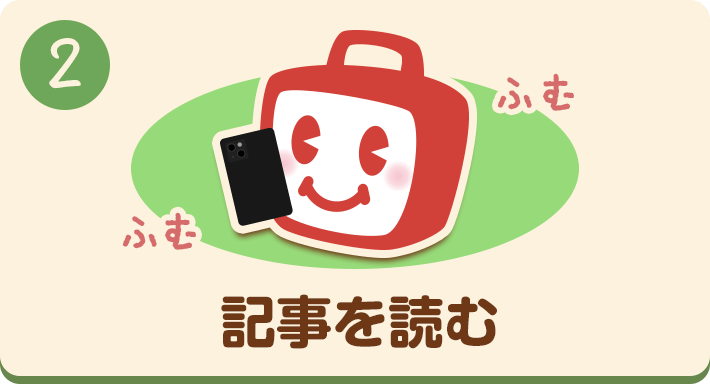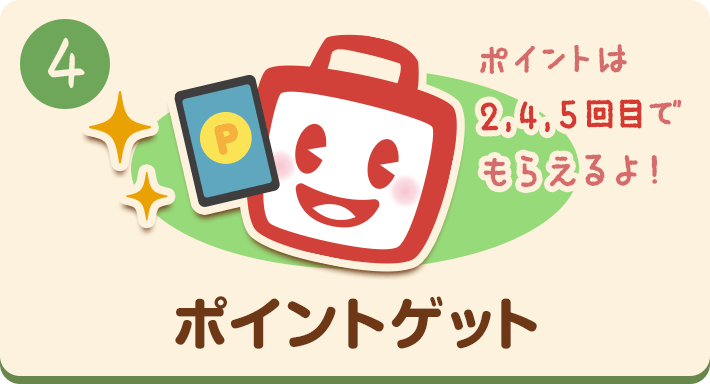歩兵が携行する対戦車火器として広く用いられている「無反動砲」、これを装甲車に載せて運用しようとした時代がありました。ひとつはアメリカのM50「オントス」。もう1両が陸上自衛隊の60式106mm無反動砲でした。
「無反動砲」を積んだ珍しい装甲車両の開発経緯とは?
陸上自衛隊がまだ保安隊と呼ばれていたころ、アメリカ軍から戦車などを供与されていた同隊では、自前兵器調達の気運が高まっていきました。その後、陸上自衛隊となった直後の1954(昭和29)年11月、三菱重工、小松製作所、日野ディーゼルの3社が防衛庁技術研究所から国産の無反動砲を搭載した車両の開発を打診されます。これが戦後初の対戦車戦闘をする車両となる60式自走106mm無反動砲でした。
 陸上自衛隊の60式自走105mm無反動砲。写真は射撃時のスタイルで、多少、砲を左右に振ることが可能(柘植優介撮影)。
陸上自衛隊の60式自走105mm無反動砲。写真は射撃時のスタイルで、多少、砲を左右に振ることが可能(柘植優介撮影)。
同車両は、1954(昭和29)年から自衛隊が開発に着手していた無反動砲「60式106mm無反動砲」を搭載する装軌装甲車(履帯、いわゆるキャタピラで動く装甲車)として開発されました。「自走無反動砲」という珍しいもので、世界中で探しても、当時のアメリカ海兵隊で運用されていたM50「オントス」自走無反動砲くらいしか、無反動砲をメインの武装として装備した装甲車両はありません。
その「オントス」の情報も乏しいことから、手探りの状態で、戦後初の国産装甲戦闘車両の開発は行われました。ごく初期にこの計画から手を引いた日野をのぞき、三菱と小松の2社による競争試作が行われ、小松の製作車両「SS-1」は三菱の「SS-2」より支持を集め、60式自走106mm無反動砲として採用されることになります。
なぜ60式自走無反動砲のような車両が必要だったのか
なぜ、このような世界的に見てもユニークな車両が、対戦車車両として採用されたのでしょうか。それは当時の、自衛隊の考える戦法が関連しています。
当時は東西冷戦の初期で、仮にソビエト連邦などの車両が本土に侵入した場合は、数に勝る相手から防衛をしなければいけない関係上、直接砲火を交えるのではなく、目標戦車から発見されずに、日本本土の地形の起伏を利用し、待ち伏せで目標を撃破することをおもな戦い方としていました。そのため車高は1.38mとかなり低くなっています。
これは後の61式戦車でも共通している点で、砲塔以外を隠し車体を防御する「ハルダウン」という戦い方をするために、砲塔の装甲を車体より分厚くしています。しかし、60式自走106mm無反動砲には、61式戦車のような装甲はなく、アルミ合金製だったため、反撃された場合は無力に等しく、撃ったらその場から即離脱することが必要でした。
そして、生存率を高めるためには確実に目標に砲弾を命中させる必要がありました。しかしその射撃は、まず豊和製の12.7mmスポットライフルで曳光弾(発行体を内蔵した弾丸で、弾道を目視するために用いられる)の光跡による照準を行い、目標に曳光弾が命中したら即、主砲から発射するという手順を踏むものでした。ちなみに自動装てん装置はないため、2発外した場合は装てん手が車外に出る必要があり、敵戦車がいる戦場で再装てんはほぼ不可能です。
同様の装備は後にナシ 60式自走106mm無反動砲の果たした役割
戦後、無反動砲の命中率はかなり向上したといわれていますが、前述のような戦法や射撃方法がどこまで有効だったかは、幸い、この車両が実戦を経験していないので謎のままです。似たようなコンセプトの「オントス」に関しても、初期に考えられていた対戦車戦闘には一度も使われず、ベトナム戦争で歩兵の火力支援にのみ使われていたので、自走無反動砲の対戦車能力は未知数のままです。
 60式自走105mm無反動砲、砲を下げた走行時のスタイル(柘植優介撮影)。
60式自走105mm無反動砲、砲を下げた走行時のスタイル(柘植優介撮影)。
ただ、1960年代以降には、強力な対戦車ミサイルや無反動砲を歩兵が携行武器として扱う機会も増えたため、戦車がない場合は結局、人が対戦車戦をした方が待ち伏せの効果も高まり、リスクが少ないという判断なのか、自走無反動砲というタイプの兵器は「オントス」や60式自走106mm無反動砲の後には続きませんでした。しかし後者に関していえば、ディーゼルエンジンや足回りなど旧陸軍の技術が活かされており、旧陸軍から陸上自衛隊に戦車技術を継承させたという面では大きな役割を果たしているかもしれません。
60式自走106mm無反動砲は61式戦車と同じく、特撮怪獣映画の黎明期にいわゆるやられ役として登場していますが、実際のところはともあれ実戦に臨んだのが創作物の中だけだったのは幸福だったといえるでしょう。