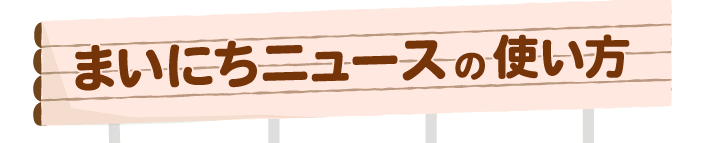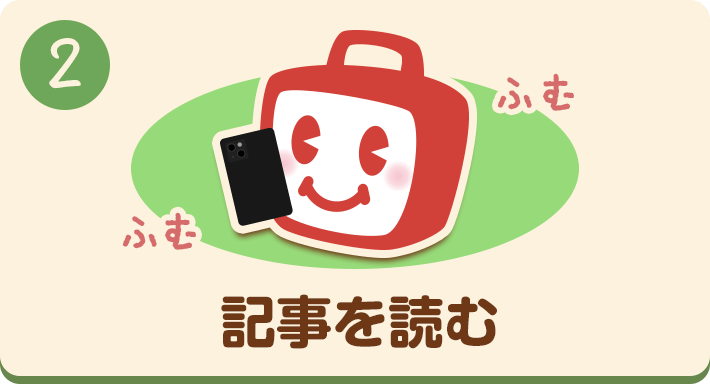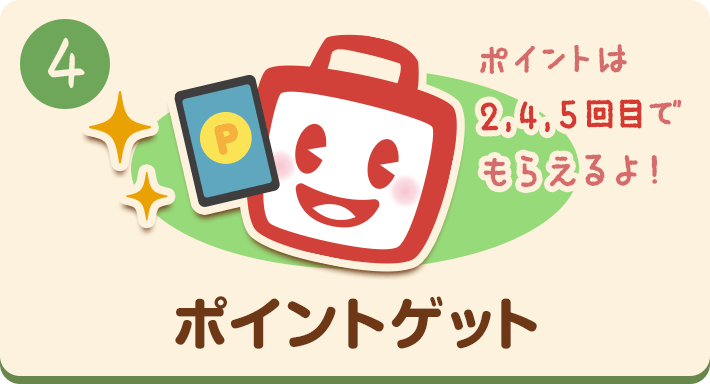孤独は「寂しい」というイメージがつきものですが、一人でいることを楽しめる人も確かにいます。孤独でも平気な人と孤独だと不安になる人は、何が違うのでしょうか。孤独を受け入れる方法も含め、心理カウンセラーのうるかすさんに聞きました。
Q.そもそも、心理的に「孤独」とはどのような状態を指すことが多いのでしょうか。
うるかすさん「『周りにどれだけ人がいるか』ではなく、『分かってくれる人がいる』『人とつながっている』『何かしらに所属している』『必要とされている』といった感覚をどれだけ持てているかにかかっているかと思われます。そうした感覚を持てない状態を『孤独である』という風に考えます。
そのような感覚を抱きやすい人の特徴として、ご自身の弱みをなかなか表に出せない、あるいは本来の自分を素直に表現できないといった傾向が挙げられるかと思います。
また、自分の弱さを安心して人にさらけ出せるかどうかは、その人がどれほど精神的に安心感を得られているかに大きく左右されるものと考えます」
Q.では、孤独が平気な人、孤独が苦手な人の違いについて、教えてください。
うるかすさん「まず、孤独が苦手な人の特徴を考える際、小さい頃の愛着関係が大きく影響しているとみられます。特に、愛着関係がしっかり築かれていない場合は自立性が育ちにくく、『自分と他人の境界線』が曖昧になることがあります。また、『自分は大切な存在である』という有能感が希薄になる傾向もあります。
そうしたことをきっかけに、自分と他人の区別が曖昧になると、自分にとって不必要な人間関係を維持したり、むしろ自分を傷つけるような人との関係性に自ら入っていってしまったりすることがあります。例えば、幼少期に否定ばかりされていると、自分の感覚を信じることができなくなり、その結果、常に他人からの意見や評価を判断の基準にせざるを得なくなることなどが考えられます。
誰かが『良い』と言ってくれることで初めて安心できるという心理状況では、他人に嫌われるということが自分の存在価値を揺るがすことにまでなりかねません。『他人に嫌われたくない』という意識が過度に働く人が、孤独が苦手な人の特徴と言えるでしょう。
逆に、孤独が平気な人は、人間関係で『追いかけない』選択ができる人だと思っています。自分にとって不必要な関係を手放せるため、必要以上に孤独を怖がらずに済むのです。こうした判断ができるのは、幼少期に安定した愛着関係を築き、培ってきたためと考えられます」
Q.孤独を受け入れるのに効果的な方法はありますか。
うるかすさん「愛着形成が希薄か、愛着を形成できていない人は、その問題を解決するというのが一つですね。自分の中に安心感、安全感が育ち、自分は自分という感覚が確かなものになれば、過度に他人からの評価を得られないということを恐れることはなくなっていくと思います。
また、孤独に対する認識を少し変えるのも一つかと思います。どうしてもネガティブなイメージがついて回る『孤独』ですが、『孤独をあまり悪いものと思わない』という考え方も良いと思います。
心理学者のフランクルは、孤独を『人生の意味を見いだす力』だと表現しました。私たちは『元来、人は孤独な存在だ』という実存的孤立を受け入れることが重要です。息を吸うのと同じように、孤独は良しあしで判断するのではなく、人間の基本的な状態だと認識できれば、孤独に強くなれます。
また、フランクルは著書の中で『どれだけ人を深く愛しても、完全に一致することはできない』としています。人を愛するということを通して、知識だけではなく体験的にそうした認識を得ることで孤独に振り回されなくなると思います。
仏教の中にも、『あえて一人となり、自分の力を高める期間を積極的に持つ』という考え方があるそうです。このように、『孤独=ネガティブ』と捉えないのも大事かと思います。もっとも、人とつながりたいという思いは人間にとって根源的な欲求であるとも言えるでしょう。従って『孤独を受け入れる』といっても、決して『ずっと一人でいても平気な状態』を理想とするわけではないと考えます。
むしろ、自分自身と向き合い、弱さも含めた本当の姿を誰かと分かち合えるような深い関係性を持つことができるからこそ、その延長線上に『一人で過ごすことを受け入れられる自分』が育っていくのだと思います。
一見すると矛盾しているようにも見えますが、孤独を受け入れるということは、同時に『人とのつながり方』を見つめ直すことでもあるのではないでしょうか」
* * *
「孤独」かどうかは、関わりのある人の数ではなく、むしろ人とのつながり方によると考えられます。特に、孤独が平気かどうかは、幼少期の愛着関係が大きく影響していることがよく分かりました。
ただ、孤独は自分を高めるきっかけにもなるといいます。孤独に対して新しい認識を持つことで、毎日を過ごしやすくなるかもしれません。
オトナンサー編集部