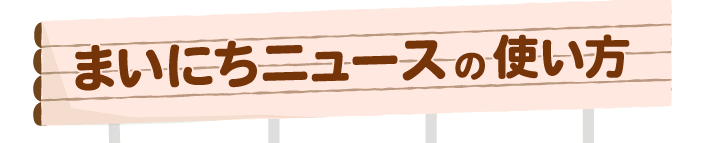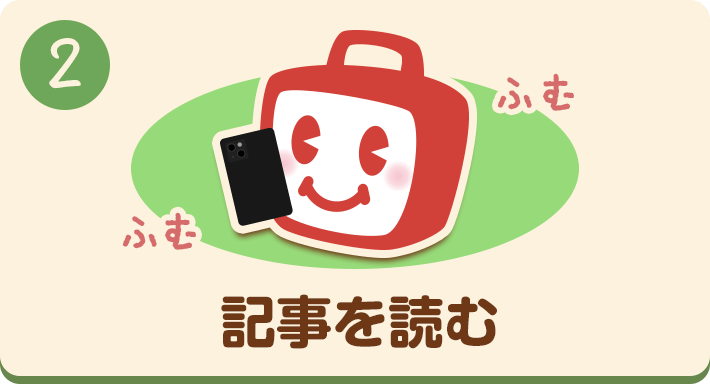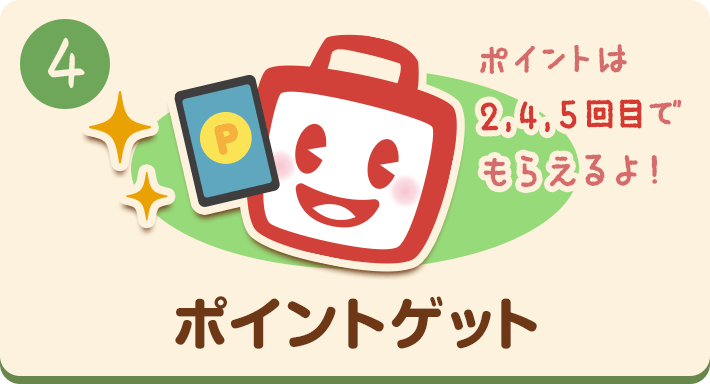徳川体制の打倒を目指した雄藩
大河ドラマ「青天を衝け」は、俳優・吉沢亮さんが演じる渋沢栄一が主人公です。渋沢は“日本資本主義の父”と呼ばれ、2024年に改刷される新1万円札の顔に決定している歴史的な偉人です。
しかし、渋沢は生家が藍玉生産・養蚕を手がける農家だったことから、青少年期は血気盛んな無名な若者でした。
武士が政をつかさどる時代において、多くの農民は名前が後世に残ることはありません。「青天を衝け」では、草彅剛さんが演じる徳川(一橋)慶喜、岸谷五朗さんが演じる井伊直弼、大谷亮平さんが演じる阿部正弘などが表舞台で活躍しています。
一方、農民だった渋沢の青少年期は事件性・ドラマ性に欠けることから、主人公にもかかわらずドラマに割かれる時間は決して多くありません。
農民だった渋沢が武士のような行動を起こすのは、尊王攘夷(じょうい)思想に染まる頃からです。幕府を打倒するべく決起し、結果的に失敗しました。
幕末には薩摩藩・長州藩・土佐藩・肥前藩という、いわゆる薩長土肥(さっちょうどひ)と呼ばれる雄藩が原動力となって徳川体制の打倒を目指します。薩長土肥のように目立つことはありませんでしたが、明治維新を陰で支えた立役者に福井藩(越前)があります。
福井藩の藩主は松平家
福井藩は徳川家康の次男・秀康によって成立。当初は67万石という大きな領地を有した福井藩は、藩主・秀康の弟だった秀忠が2代目の将軍に就いたことから、幕府からも一目置かれる存在でした。
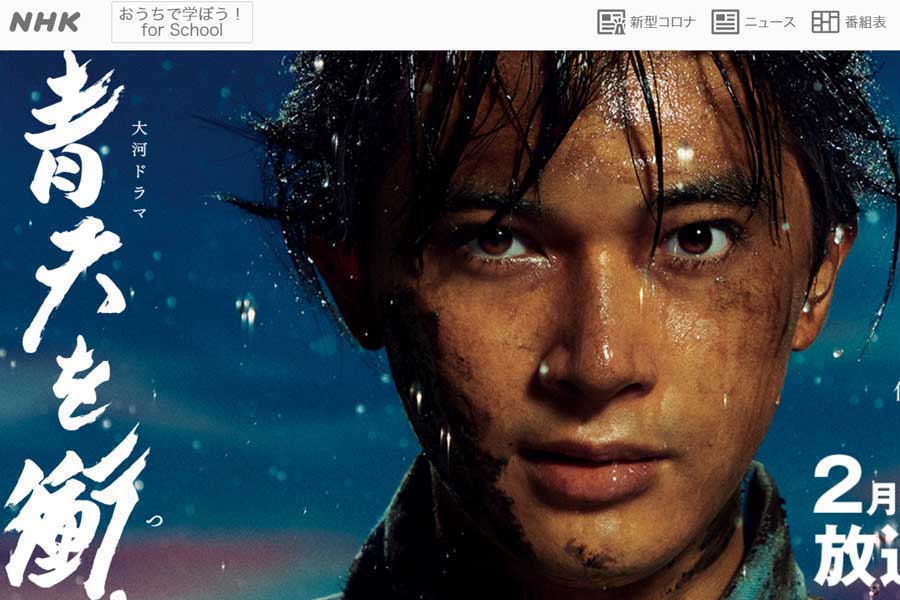
福井藩は江戸時代を通じて松平家が藩主を務めました。「青天を衝け」では、要潤さんが演じる松平慶永(よしなが)が重要人物として活躍しています。慶永は春嶽(しゅんがく)という号の方が一般的になっているため、現代では松平春嶽と呼ばれることもあります。
慶永は藩政改革を進めた名君として知られていますが、慶永が名君といわれるゆえんは自身の考えに固執することなく、柔軟に物事を捉えていたところにもあります。慶永は以前から科学技術への関心が高く、それらを取り入れるべく西洋の雑誌を取り寄せて学んでいました。
また、慶永自身が西洋知識を得るだけではなく、多くの人に学問的な素養を身につけさせようとして明道館(めいどうかん)という学校を開校。そこで福井藩士の子弟に学問を学ばせるなど、教育にも熱心でした。
慶永を支えた、後の東京府知事
当初、慶永は強硬な攘夷論者でしたが、福井藩士の橋本左内などが開国を主張。その影響を受けて、慶永も次第に考えを開国へと傾けます。また慶永は、後に東京府知事に就任することになる由利公正(きみまさ)を起用し、藩財政改革にも着手。由利の取り組んだ藩財政改革は後に東京府政にも生かされることになります。

西洋知識を貪欲に取り入れようとする慶永の姿勢は、福井藩政にも大きな影響を与えます。慶永は1858(安政5)年に発生した安政の大獄で隠居させられてしまいますが、跡を継いだ松平茂昭は幕府が鎖国を解いた後に海外の進んだ率先的に取り入れるべく、福井藩士を海外留学させているのです。
福井藩士で初めて海外に渡ったのは、慶永の参謀役を勤めていた佐々木長淳(ながあつ)です。
佐々木は西洋砲術の知識にたけていたことから、福井藩の軍政改革を主導。それが藩主・慶永から信任を得たのです。佐々木は貿易という仕事のために海外へ渡りましたが、勉学のために海外へと送り出された日下部太郎という福井藩士もいました。
日下は慶永の身辺警護役で周囲から勤勉家と評判の高く、そのために福井藩の公式的な留学生としてアメリカへと渡ることになりました。
アメリカのラトガース大学で学んだ日下部でしたが、滞在中に肺結核に罹患(りかん)。日下部は留学費用の捻出にも苦労していたこともあり、満足に医者にかかることもかなわず現地で死去してしまいます。
しかし、ラトガース大学で日下部を指導していたウィリアム・エリオット・グリフィスが、1871年にお雇い外国人として来日。福井藩の設立した明道館は明治新政府の発足に伴い明新館と改称していましたが、グリフィスはそこに着任して理化学・数学・英語などの講義を担当しました。
お雇い外国人の功績
明新館ではグリフィスよりも先に、イギリスからお雇い外国人として召し抱えられていたアルフレット・ルセーによる講義が始まっていました。そこにグリフィスが着任。教育的な地盤が整い、福井の教育は充実していきます。
グリフィスを教師として迎えるにあたり、福井城の近くに居宅となる洋館が新築されました。開港場の横浜や神戸、政治の中心地である東京に比べれば、福井では外国人や洋館はまだ珍しい存在でした。そうした環境から、グリフィスの洋館が完成した時には、多くの見物客であふれたようです。

グリフィスは主に化学を教えていましたが、実験器具などが乏しく、満足な授業ができませんでした。実験器具を手に入れるため、東京の大学南校(現・東京大学)に出向くこともあったようです。
親日家だったグリフィス
さまざまな苦労があったグリフィスの教師生活ですが、それでも福井の暮らしに満足していたようです。

ところが、自身を雇い主でもあった茂昭が廃藩置県によってお役目御免となり、グリフィスを招聘(しょうへい)するために世話をしてくれた旧福井藩士たちも次々と福井を去りました。それらが重なって、グリフィスの福井滞在も約10か月と短い期間でピリオドを打ちます。
福井を後にしたグリフィスは、大学南校の教壇に立ち、約2年半にわたって後進の指導にあたります。
グリフィスが大学南校で再び教鞭(きょうべん)をとれたのは、由利が推薦したからです。そして、グリフィスから薫陶を受けた若者たちのなかには、福井を去るグリフィスを慕って東京南校へと転学する若者もいました。
福井の人々に慕われたグリフィスは、帰国後に『The Mikado’s Empire』という日本の文化や風土を紹介する滞在記を刊行。後に『皇国』と邦訳されてもいます。ちなみに同書の執筆にあたっては、明新館と大学南校でグリフィスの教え子だった今立吐酔(いまだて とすい)が執筆作業のサポートをしています。
グリフィスが執筆していた当時、今立はペンシルベニア大学に留学中でした。そのために協力ができたのです。
グリフィスは親日家でもあり、1926(大正15)年に再来日を果たします。約1年半もの長期滞在では、日本各地を周遊していますが、自身が教鞭をとった福井にも足を運びました。グリフィス自身も福井に強い思い入れがあったようですが、福井の人たちも熱烈に歓迎しています。
幕末期、そして明治維新期に薩長土肥だけではなく、福井が優れた人材を輩出できた理由のひとつには、学問という素地(そじ)が大きかったようです。